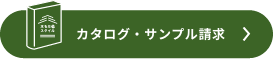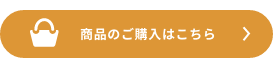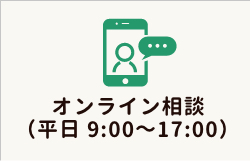2018.11.21
ひとつひとつ違う石の性質を把握し、頭の中に配置を組み上げる「石積の技」
山本です。
秋が深まりゆくのを日に日に感じますね。
小川社お昼休みに会社近辺を散策しますと、
美しい石垣が見られます。

▲ワイルドな石垣

▲石垣四段
話しは逸れますが、
自然石をそのまま積み上げる「野面積み」を代表する積み方を穴太衆積みとよばれています。
一見粗野に見えますが、強度には比類なきものがあります。戦国時代、織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちにした際、その石垣の堅牢さに驚き、坂本・穴太・滋賀里あたりに住んでいた石工職人たちを集めて安土城を築城したほどだといわれています。
彼らが石の組み方を考える際には、石の集積場に行き、たくさんの石の周りを1、2日かけて周りながら、ひとつひとつ違う石の性質を把握し、頭の中に配置を組み上げるとか。宮大工の西岡常一氏は「木の声を聴く」と言われましたが、石積みの職人達は「石の心の声」を聞くことができるのでしょう。
会社近辺の石垣は、そこまでの石垣ではないとしても
会社から徒歩圏内でこんなにもバリエーション豊かな石垣が
見られるのはここ尾鷲市賀田町の魅力の一つでは
ないでしょうか。
▲組み方が違う石垣

▲石垣2段
 ▲石垣斜壁
▲石垣斜壁
近年ではコンクリートブロックが多くなりましたが、
滋賀県大津市にある「ピアザ淡海」の玄関、
新名神高速道路の護岸壁などに穴太衆積みの石垣が採用されたそうです。
新名神高速道路工事の際には、穴太衆積みとコンクリートブロックを比較する強度計算を行ったのですが、なんとコンクリートの1.5倍から2倍の強度があることが判明されたとか。
弊社では、「代々培ってきた技術を今の時代にあわせて提案しよう」と取り組んでいます。スタッフ山本がブログ用の文章をよみ、会社から徒歩圏内の中にも長年にわたり改良を重ねた技に気づかされました。(感謝)
(文:山本 編集:百合子)
(参考資料:穴太衆 石積みの極意と家訓